銀行116行の国債残高 162兆円
国内116銀行の2013年3月期の預証率が2年連続で40%を超えた。金融円滑化法などで企業倒産は沈静化しているが、金融機関の中小企業向け貸出しは低迷している。金融機関が「貸出リスク」回避の姿勢を強めた結果、有価証券の資金運用が高まり国債残高は162兆円に膨らんでいる。
- ※本調査は、国内116銀行を対象に2013年3月期単独決算ベースの預証率を調査した。銀行は預金等の調達資金を貸出し、余資を有価証券などで運用している。預証率は預金残高に対する有価証券残高の比率で、金融機関の資金運用状況を示す指標の一つ。
預証率=有価証券÷(預金+譲渡性預金)で算出し、有価証券は貸借対照表の資産の部に計上されている「国債」、「地方債」、「社債」、「株式」、「その他の証券」を合計した。「預金」と「譲渡性預金」は、貸借対照表の負債の部から抽出し、合計した。
2013年3月期の預証率40.8% 2年連続で40%超
116銀行の2013年3月期単独決算ベースの預証率は40.8%で、2年連続40%台の高水準だった。預証率を3月期ベースで比較すると、2006年35.8%、07年33.9%、08年31.3%と戦後最長の景気拡大を背景に、貸出しが堅調に推移し低下傾向にあった。だが、リーマン・ショック以降の09年は31.8%、10年は36.7%、11年39.8%と上昇に転じた。銀行貸出しが低迷し、急速な市場悪化から株式、社債の比率が低下し、国債への資金流入の急増を裏付けている。また、長期化する欧米の景気低迷、歴史的な円高で大手企業の設備投資意欲は減退し、中小企業向け貸出にしは一層慎重になった。この結果、12年に41.8%と調査開始以来、初めて40%台に乗せ、この傾向が続いている。
預金に対する貸出残高を示す預貸率は68.9%(前年同期69.2%)で、4年連続で前年同期を下回った。銀行資金が貸出しに向かわず、有価証券運用にシフトしていることを端的に示している。
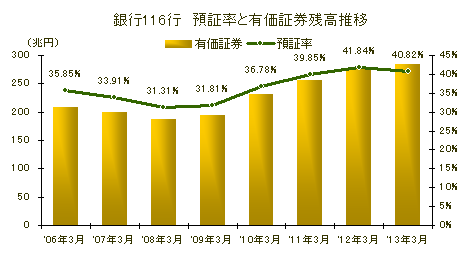
国債残高162兆円 有価証券の約6割を占める
116銀行の2013年3月期の有価証券残高284兆3,060億1,100万円のうち、「国債」は162兆7,738億9,700万円(前年同期比2.1%減)だった。「国債」が有価証券運用の約6割(構成比57.2%)を占めていることがわかった。
3月期の国債残高は、2006年が92兆9,748億6,300万円、07年が82兆455億7,300万円(前年同期比11.7%減)、08年は77兆4,340億4,100万円(同5.6%減)と減少に転じた。ところが、リーマン・ショックを経た09年は95兆8,145億9,500万円(同23.7%増)と急増。以降、10年は130兆4,558億4,700万円(同36.1%増)と100兆円台に乗せ、続く11年150兆9,148億2,000万円(同15.6%増)、12年166兆4,330億7,200万円(同10.2%増)と急速に流入をみせた。2013年3月期は前年同期こそ下回ったが160兆円台を維持している。
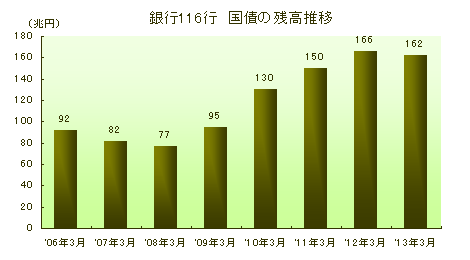
大手行・信託銀行の預証率 前年同期比2.7ポイント低下
業態別の預証率は、地銀64行が31.8%(前年同期比0.8ポイント増、前年同期31.0%)、第二地銀41行が26.4%(同0.9ポイント増、同25.5%)、大手行・信託銀行11行が48.3%(同2.7ポイント減、同51.0%)だった。地銀、第二地銀とも預証率が前年同期より約1ポイントアップしたが、大手行・信託銀行は2.7ポイント下げて二極化の動きがみられた。
地銀、第二地銀の国債残高 前年同期比1.7%増
業態別の国債残高は、地銀64行が35兆1,566億8,100万円(前年同期比1.7%増)、第二地銀41行が7兆7,770億4,900万円(同1.7%増)と増加した。これに対し、大手行・信託銀行は119兆8,401億6,700万円(同3.5%減)で前年同期を下回った。大手行・信託銀行では、積み上がった国債について将来の金利上昇を含めたリスク管理を強める動きがあり、影響したとみられる。
国債残高 65行で前年同期を上回る
国債残高の個別増減額は、116行のうち65行(構成比56.0%)で前年同期を上回った。増加額が最も大きかったのは、三菱UFJ信託銀行の1兆1,049億5,800万円増。次いで、七十七銀行4,160億500万円増、中国銀行2,531億5,200万円増、栃木銀行2,345億6,300万円増、静岡銀行1,968億1,100万円増。増加額が100億円を超えたのは43行(構成比37.0%)を数えた。
一方、49行(構成比42.2%)が前年同期を下回った。最も減少額が大きかったのは三井住友銀行の2兆2,412億円減。次いで、三菱東京UFJ銀行9,153億円減、りそな銀行8,032億円減、埼玉りそな銀行6,769億円減、みずほ信託銀行4,455億円減と大手行が上位を占めた。未計上は2行。
大手行・信託銀行 11行のうち8行で国債残高が減少
業態別の国債残高の増減額は、地銀64行が前年同期と比べ38行(構成比59.3%)が増加、減少は25行(同39.0%)、未計上が1行だった。第二地銀41行は、24行(構成比58.5%)が増加、減少は16行(同39.0%)で、未計上が1行だった。地銀と第二地銀は、ともに約6割の銀行で国債残高が増加した。
一方、大手行・信託銀行11行では、8行(構成比72.7%)が減少、増加は3銀行にとどまり、7割で減少した。大手行・信託銀行は、政権交代でデフレ脱却の方針が明確になり、将来の金利上昇リスク(国債価格の下落)に備えて長期国債から短期保有の国債を増やす動きもあり、株式や外国債券への資金シフトを進めている。今回の調査結果でも、この動きを裏付けた。
銀行の中小企業向け貸出しは低迷しているが、国債を中心とした有価証券の運用は拡大している。なかでも、銀行の膨大な国債保有残高は、銀行貸出しの「リスク回避」姿勢の反映とみることができる。今年3月末に「中小企業金融円滑化法」が終了したが、企業の成長支援には銀行貸出しが欠かせない。こうした状況で、資金運用が低利回りの国債に流入にしていることは心もとない。国債金利が上昇傾向をみせているが、アベノミクスで景気拡大への動きが見え始めたなか、今後の銀行貸出しの推移と株式・外国債券などへの運用シフトの動向が注目される。














