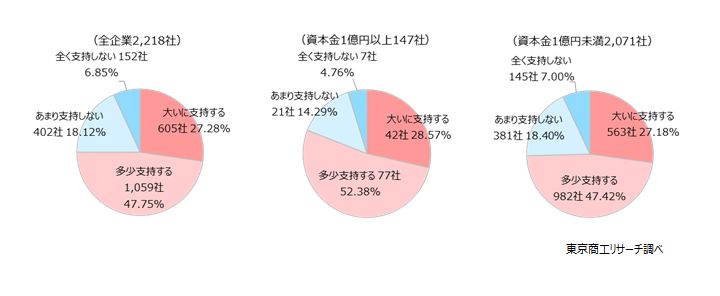早期事業再生法、成立の背景と意義 ~島田充生弁護士、関彩香弁護士インタビュー ~
過剰債務や物価高、人手不足などで2024年度の企業倒産は1万144件(前年同期比12.0%増)と、11年ぶりに1万件を超えた。
経済的に苦境に陥るおそれのある事業者が早い段階での事業再生に取り組む環境を整えるため、2025年6月に早期事業再生法(※1)が成立。26年12月中旬までに施行される。
私的整理は、純粋私的整理とルールに基づいて対象債権者と債務者の合意を目指す準則型私的整理に分けられる。後者で有名なのは、事業再生ガイドライン(※2)や事業再生ADRだ。公正中立な第三者が関与して行われる手続きで実務の積み上げも進んでいる。非公開で進めるため、事業価値の毀損を最小化できるが、対象債権者の全員同意が課題だった。
早期事業再生法により、第三者機関のもとで、多数決と裁判所の認可で債務の調整を進めることが可能となる。
※1 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律
※2 中小企業の事業再生等に関するガイドライン
東京商工リサーチ(TSR)は、再生実務に詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所(AMT)の島田充生弁護士、関彩香弁護士に法の概要や注目点などを聞いた。
島田充生弁護士
2013年に弁護士登録
認定経営革新等支援機関認定
2022年英国事務弁護士登録
事業再生、倒産、M&A等の事案に強みを有する
関彩香弁護士
2013年に弁護士登録
2021年ニューヨーク州弁護士登録
―早期事業再生法の概要は
早期事業再生法は、債権者の多数決と裁判所の認可を条件として、金融機関等が保有している貸付債権等について権利変更ができる制度だ。既存の準則型私的整理は、全対象債権者の同意が必要だったが、議決権の総額の4分の3以上の同意で権利変更が可能となる。

インタビューに応じる島田弁護士
ただ、単一の債権者が議決権の総額の4分の3以上を有する場合には、対象債権者集会に出席した議決権者の過半数の同意(頭数要件)も必要で、少数債権者への配慮もされている点が特徴だ。また、手続きには裁判所も関与するものの、非訟事件とされ、公告はされず、非公開の手続きとなる。
早期事業再生法は、権利変更の対象を金融機関等が保有している貸付債権等に限定しているため、公租公課の滞納や商取引債権の未払などがある債務者の状況を直接解決するものではない。
事業者が指定確認調査機関に手続きを申請し、確認作業を経た後、原則として6カ月以内に早期事業再生計画および、権利変更議案を作成し、提出する必要がある。
現在、早期事業再生法の施行に向けてワーキンググループが設置され、有識者が対象債権者や対象債権の範囲、従業員から協力を得るための措置、資産評定基準など運用面について協議中だ。
―法律が成立した背景は
早期事業再生法が成立したきっかけの1つが、2022年のマレリホールディングス(株)(TSRコード:022746064、さいたま市北区)のケースだ。債権者が多数にのぼり、海外債権者を含めた全行同意が難しく、事業再生ADRが不成立になり、民事再生(簡易再生)に至った経緯がある。
そのため、早期事業再生法は、対象債権者の数が多い場合や、海外債権者が存在する場合など、全行同意が確証をもって進められないケースなどで使われることが想定される。
例えばイギリスでは、組織再編手法としてスキーム・オブ・アレンジメントなどが利用されるなど、債権者による多数決と裁判所の認可で進める手続きは海外にも存在する。海外債権者にとって、全行同意よりも多数決が馴染み深く、早期事業再生法の成立により、グローバルスタンダードに近づいたといえる。
また、事業再生計画案成立に対する予測可能性が高まる結果、新たなプレーヤーが参入するなどして、日本の不良債権マーケットが活性化する契機になるかもしれない。
ただ、いずれにしても、早期事業再生法が成立したからといって、少数債権者をないがしろにして良いというわけではない。残高の多寡に関わらず、各金融機関との信頼関係を醸成することが、これまでと変わらず重要だ。
―事業再生ADRなどとの違いは
前述の決議要件の違い以外に、早期事業再生法は、権利変更となる対象債権者の範囲が金融機関かつ、対象債権は、その保有する貸付債権等(担保により保全された債権は権利変更の対象外)と厳格に定められているが、事業再生ADRは、金融機関等でなくとも、相当と認められる債権者が応諾すれば、手続きに取り込める点が異なる。

関弁護士
また、早期事業再生法は事業再生ADRよりも、指定確認調査機関の確認後になされるつなぎ融資(プレDIPファイナンス)の保護の範囲が広い点なども注目される。
早期事業再生法は、手続を利用する要件の一つとして、事業者が「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれがある」ことを挙げているとしている。これに対し、事業再生ADRでは、債務者の要件として、「過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力による再生が困難であること」を求めているところ、早期事業再生法は、より早期の段階で手続きを利用できるように設計されているように思われる。
そのほか、事業再生ADRでは裁判所の関与はないが、早期事業再生法では、強制執行や担保権実行の中止命令に加え、権利変更決議の認可決定を行うなどの一定の役割が裁判所に与えられている点も大きな特徴だ。
事業再生ADRも、早期事業再生法も金融機関の意向を無視して進めることは出来ない。早期事業再生法は事業再生のための選択肢が1つ加わるイメージだ。企業にとってどの手続きが最適かを議論し、ベストな手続きを選んでいくことが重要だ。
インタビューの最後に、事業再生の手法が多様化していることについて尋ねた。島田弁護士は、「我々実務家からすると、支援メニューが増えることはポジティブに捉えている。一方で、多様な方法があることで、より一層、倒産実務家の力量が重要になってくる。私自身も頑張っていきたい」と語っていたのが印象に残った。
企業倒産は緩やかに増勢をたどり、事業再生支援へのニーズは高まっている。
再建型の法的倒産は公告されるため、レピュテーションリスクが避けられない。再建型の民事再生法の利用件数が減少しているなか、まずは私的整理が第一候補となることも多い。倒産の手前で事業再生を目指す企業にとって、多数決による権利変更など弾力的な運用は大きなメリットになる。
2026年12月の早期事業再生法の施行を前に、実行フェーズに向けた協議が注目される。
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2025年11月10日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)