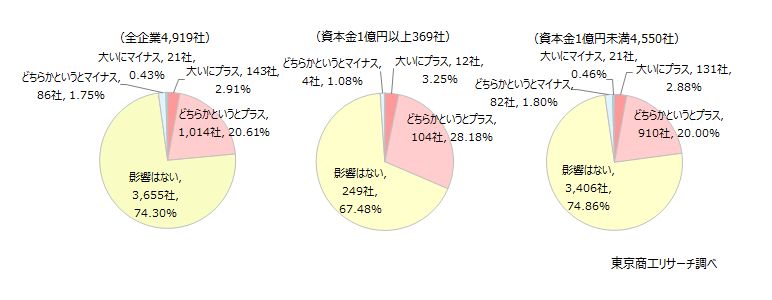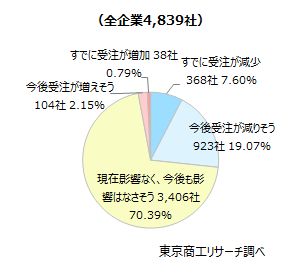金融機関や弁護士だけでなく、中小企業支援者全体のバイブルに ~ 「事業再生ガイドラインのすべて」執筆者インタビュー(前編) ~
2022年3月に「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(以下、GL)が公表されてから1年半が経過した。官民が歩調を合わせて普及に向けて取り組む中、2023年9月に「中小企業の事業再生等に関するガイドラインのすべて」(以下、本書)が商事法務より刊行された。
東京商工リサーチ(TSR)は、GLの策定に携わり、本書を執筆・編集した小林信明弁護士(長島・大野・常松法律事務所)と編集委員の横田直忠弁護士(阿部・井窪・片山法律事務所)にGLの現状や刊行の意図、事業再生の動向などを聞いた。
―本書を刊行した目的は
(小林)GLは新しい制度であり、本文とQ&A(※1)だけでは内容が伝わりにくい部分もあるだろう。適切に活用していただくには、策定の背景や目的を基にした解説書が必要ではないかと考えた。また、GLをより周知してもらう狙いもある。
(横田)本書の執筆者はGL策定の関係者を中心としている。この意味でも本書はGLの運用実務の指針になるのではないか。
※1 GLは「目的」、「基本的な考え方」、「手続」の3部から成る本文と、実務手引きのQ&Aで構成される
―想定読者は
(小林)金融機関や弁護士、商工団体、中小企業など。
(横田)税理士や中小企業診断士にも読んでいただきたい。GLの第二部は金融機関と中小企業のあるべき姿が双方の視点から初めて書かれたという点で、これまでにないバランスの取れた存在だ。中小企業支援において第二部を参照する実務が広がるとありがたい。

GLの意義を説明する小林弁護士
中小企業活性化協議会(以下、協議会)の収益力改善支援(※2)の要領でもGLが引用され、平時の予防的対応に当たる支援だと記載されている。第二部をきっかけに、新しい支援策や金融機関と中小企業との対話が促進されていくと、GLの価値がさらに高まっていくのではないか。このため、弁護士以外の士業の方にも参照いただきたい。
※2 1~3年に渡る収益力改善アクションプランと簡易な収支・資金繰り計画の作成を支援する
―GL運用開始から1年以上が経過した。課題は
(小林)GL策定当初から、第三者支援専門家の数が少ない(※3)との問題意識はあった。特に、第三者支援専門家が大都市に偏りがちだということは認識していた。一方で、GLが信頼性を保ち、社会的に認められるためには、公正中立で透明性のある手続きが進行されなければならず、第三者支援専門家の質も重要だ。補佐人制度(※4)等を積極的に活用して私的整理の経験を積んだ実務家が第三者支援専門家候補者になることで、質を重視しつつ不足を解決していく取り組みも重要であろう。
(横田)GLの周知普及が課題だと感じている。GLで規定された廃業型私的整理手続で円滑な廃業を行い、(中小企業債務の保証人の)自己破産を回避し再スタートをしやすくする世の中を作ることには強くこだわってきたが、リース債権者や貸金業者にまでGLが浸透していない。
※3 2022年9月20日時点の第三者支援専門家リストによると、総数169人のうち、東京が91人、大阪が21人で、宮城や埼玉など15県はゼロ
※4 第三者支援専門家の補佐人の経験を第三者支援専門家の認定要件とする制度

GL策定の背景を説明する横田弁護士
―準則型私的整理は金融債権を対象とするが、金融機関だけでなく、サービサーや貸金業者も対象債権者になる可能性がある。実効性の確保は
(小林)サービサー協会(※5)での講演などを通じてGLへの理解を呼び掛けている。実効性の確保については、金融機関が債権譲渡する際、譲受人のGL遵守を前提にするなどが考えられる。譲渡側にはこうした働きかけを期待している。
※5 一般社団法人全国サービサー協会
―GLの第二部では、金融機関と中小企業の平時の付き合い方について書かれている。改めて、この意義について
(小林)金融機関と債務者である中小企業の平時の付き合い方が重要というのは従前から認識され、これまであり方が議論されてきた。その議論も踏まえ、金融機関と中小企業の平時の付き合い方を明記した。他の準則型私的整理では、債務整理の部分しか書いていない。平時から金融機関と信頼関係を構築することが有事に活きてくる。その点を強調したかった。
―GLは中小企業の行動も規定するのか
(小林)GLの特徴は、金融機関にやるべきことをしっかりやってもらうが、中小企業もやるべきことをやってくださいと明記しているところだ。信頼関係を保つために双方に求められることを具体的に明示したので、平時の付き合い方の重要性に関する認識をさらに深めると同時に、金融機関と中小企業それぞれのやるべきことが明確になった。
また、中小企業が倒産すると、多くのケースで粉飾が見つかる。経営者に粉飾した理由を聞くと、「粉飾をしたくなかったが、金融機関に正直に話すと貸出が止められるかもしれないという危惧があった」と言う。粉飾を肯定する意図はないが、虚偽の財務情報では金融機関としても適切なコンサルティングができず、信頼関係も成り立たない。それはお互いにとって不幸だ。中小企業が誠実に情報を開示し、金融機関も情報開示を受けたなら、それだけをもって不利益な取り扱いをしないことが重要だ。金融機関がそうした姿勢を示さないと、中小企業も適切な情報開示ができない。粉飾があったとしても「すみませんでした。これからちゃんとやります」と言えるような土壌を作りたかった。そのきっかけになれば良いと思っている。
―第三部に廃業型が入った意義は
(横田)政府全体として「再チャレンジがしやすい世の中を作っていこう」というのは、非常に重要な取り組み(※6)だと思っている。特に、コロナ禍で傷んだ中小企業が先の見えない不安感を解消し、少しでも早く経営改善に踏み切れるようにするには、円滑な廃業に向けた仕組みも必要だ。GLが周知されることで、ポジティブに経営改善に向けた取り組みへ着手できる中小企業が増えてほしい。
※6 GL策定当時、横田弁護士は中小企業庁事業環境部金融課に出向していた
―金融機関にとってのGLのメリットは
(横田)経営が破たんするギリギリまで粘ってしまうと、金融機関に対する弁済は当然見込めないが、早めに話し合いを持つことで破産手続より多くの回収が見込める。実際に、金融機関から、廃業型私的整理を進めたい、という相談を受けることも多い。
―GLには必要に応じ「地域経済に与える影響」も鑑みた内容にするよう明記されている。廃業に取り組むことによる地域の好循環についての整理は
(小林)廃業型私的整理がスムーズな手続きとして設けられていることは、金融機関と中小企業が円滑な話し合いに進むための助けになる。早期に着手することで金融機関の弁済額が増えるという経済合理性があり、商取引債権は弁済するため取引先に混乱がないという点で地域経済にもメリットがある。
―協議会とGLの棲み分けは
(小林)案件によってはGLの方が良いケースもある。典型例は協議会が手続主宰者にならない廃業型(※7)だ。また、再生型で早期にスポンサーがつき、早急に処理する必要があるような事案ではGLが適切な場合もある。加えて、中小企業の事業再生ニーズは多く、協議会だけでは対応しきれない場合にGLを使うこともあるだろう。
※7 協議会でも「円滑な廃業」に向けた取り組みはあるが、再チャレンジを念頭にしている
―GL的なものを望む声は以前からあった。コロナ禍のような事態を経ないと実現できなかったのか
(小林)平時も含めたGLというのは、コロナ前から作るべきだという意見があった。コロナ禍において協議会に相談する中小企業が急増したこともあり、行政の働きかけもきっかけになっている部分はある。
(続く)
(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2023年10月12日号掲載「WeeklyTopics」を再編集)