国内407金融機関(2012年9月末時点) 「中小企業金融円滑化法」に基づく返済猶予の実績調査
国内407金融機関の2012年9月末の中小企業金融円滑化法に基づく返済猶予の申込件数のうち、住宅ローンを除く中小企業向け申込件数は390万5,165件(金額106兆1,269億2,600万円)で、実行件数は363万2,558件(実行率93.0%)だった。実行金額は99兆5,591億7,500万円(同93.8%)で、実行率は2012年3月末より件数で0.7ポイント、金額で0.6ポイント上昇した。
謝絶(3ヵ月以上経過のみなし謝絶含む)は、8万9,277件(金額2兆4,091億600万円)で、申込件数の2.2%にとどまり、審査中は7万1,571件(同2兆166億1,600万円)だった。債務者の意思による申込撤回や倒産などによる「取下げ」は11万1,759件(同2兆1,414億7,900万円)だった。
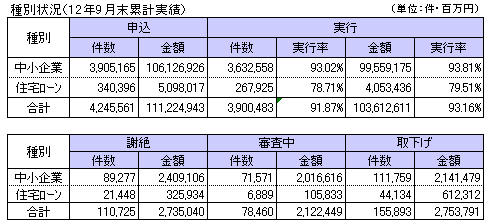
2009年12月に施行された金融円滑化法の期限切れまで、あと3カ月を切った。金融庁は、中小企業者等の事業再生等に向けた「ソフトランディング」策として2013年3月末まで再延長した。金融円滑化法と緊急保証・セーフティネット保証(5号)の政策効果が中小企業の資金繰り緩和に大きく寄与し、企業倒産は抑制された。
2012年度上半期(2012年4-9月)では、2011年度下半期(10月-2012年3月)より中部(5.9%増)、北陸(1.9%増)、四国(1.5%増)と、9地区中3地区で倒産件数が増加した。また、47都道府県のうち14県で増加した。倒産原因として「既往のシワ寄せ」が増えていることからも、政策に支えられていた中小企業が息切れの状態に陥っているものとみられる。
本調査は、国内407金融機関(大手8行、地方銀行64行、第二地銀41行、信託銀行6行、政府系金融8行、ネット銀行他9行、信用金庫271金庫)を対象に、2009年12月の法律施行から2012年9月末までの中小企業金融円滑化法に基づく条件変更の実績をまとめた。
- ※407金融機関:1.埼玉りそなを含む大手行(8行)、2.地方銀行は全国地銀協加盟行(64行)、3.第二地銀は第二地銀協加盟行(41行)、4.信託銀行、5.政府系金融、6.ネット銀行他、7.信用金庫。ホームページ及び取材により実績数値を確認。
中小企業の8.2%が申請へ
中小企業等の申込件数390万5,165件に対して、仮に1社が3行に平均2回、借入2本の条件変更等を申し込んだと仮定すると、32万5,430社が申請したことになる。
これは普通法人260万836社(国税庁2010年度普通法人数)と個人事業者の消費税の納税申告件数132万8,409社(2010年度)の合計392万9,245社のうち8.2%が申し込んだ計算となる。
この試算によると、申込社数と企業数との比較では、富山県が申込率18.2%と最も高い。次いで、岐阜県が同17.5%、東京都が同14.8%と続く。47都道府県のうち、9都府県が10%以上だった。
地区別の申込率では、北陸が13.2%と最も高かった。次いで、中部9.8%、関東9.7%、四国8.6%、中国8.4%の順。申込率が5.0%未満は、北海道(4.0%)、九州(4.6%)で、地域格差が広がっている。
中小企業の実行率トップは中部 謝絶率は九州が最高
中小企業の申込件数の実行率は、中部が94.0%(実行件数59万9,909件)で最も高かった。次いで、中国93.6%(同19万7,205件)、関東93.09%(同167万2,393件)、四国93.06%(同11万3,245件)、北陸92.8%(同14万853件)、東北92.4%(同15万2,734件)、近畿92.3%(同47万7,309件)、北海道92.1%(同7万4,615件)、九州91.3%(同20万4,295件)の順。すべての地区で、実行率が90%以上だった。
地区別の謝絶率は、九州が3.4%で最高だった。次いで、四国(3.25%)、東北(3.24%)と続く。実行率が最も高かった中部の謝絶率は2.2%で、九州、東北、四国、北陸の4地区が3.0%以上であるのに対し謝絶率の低さが目立つ。また、関東は唯一1%台で最も低かった。
実行率が最も低く、謝絶率が最も高かった九州の2012年度上半期倒産は430件で、2011年度下半期457件に比べ27件(5.9%)減少した。九州は8県中で鹿児島県のみ倒産が増加し、佐賀県、沖縄県の2県は同数。
一方、中部は実行率は最も高かったが、2012年度上半期の倒産は822件(2011年度上半期776件)と、倒産件数は増加した。
金融円滑化法の活用で、中小企業の資金繰りは一時的に緩和され、企業倒産は抑制された。しかし、実行率や謝絶率と企業倒産は関連性がなくなっている。中小企業が、金融円滑化法を申込、実行されても、その後の業績が回復しないと、金融機関から新たな資金調達が難しく、企業体力も息切れ状態に陥ってきている可能性もある。
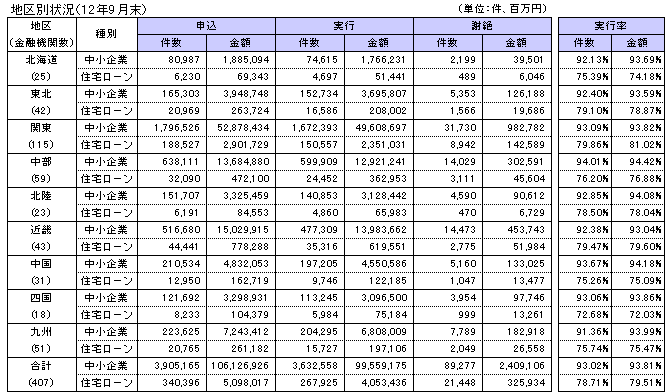
申込件数 信用金庫と地方銀行で拮抗
中小企業の申込件数を金融機関の業態別にみると、最も多かったのは信用金庫の127万345件(構成比32.5%、金額23兆5,807億5,400万円)だった。次いで、地方銀行が123万8,657件(同31.7%、金額36兆2,751億7,500万円)、大手行52万2,564件(同13.3%、金額26兆2,240億5,300万円)と続く。その他、政府系金融(43万3,661件、金額9兆387億4,400万円)、第二地銀(42万2,423件、金額10兆4,748億5,900万円)の順。
地域金融としての地域に密着した地方銀行や地元の小・零細企業を支える信用金庫の積極的な対応を示している。
実行件数は、信用金庫118万7,624件(金額22兆1,273億2,600万円)、地方銀行115万926件(同34兆1,272億2,800万円)、大手行48万1,456件(同24兆4,792億8,500万円)の順。
件数の実行率では、政府系金融が93.8%と最も高く、次いで信用金庫(93.4%)、地方銀行(92.9%)、第二地銀(92.3%)、大手行(92.1%)、信託銀行(91.0%)の順。ネット銀行他を除く6業態で、実行率が90%以上となった。
1件当たりの申込金額は、地方銀行が2,900万円、信用金庫が1,900万円と取引先の規模により格差が生じている。
まとめ
2012年11月に中塚金融担当大臣(当時)が、談話として金融円滑化法の期限到来後の検査・監督の方針を発表した。期限を迎えた後も、金融機関に対し貸付条件の変更などに応じることを求めた。その一方で、経営改善計画が1年以内に策定できる見込みがある場合や、5年以内(最長10年以内)に経営再建が達成される経営計画がある場合は不良債権に該当しない、という08年11月に改正した監督指針、金融検査マニュアル(中小企業向け融資の貸付条件緩和が円滑に行われる措置)を改めて示した。
中小企業金融円滑化法は、30万社~40万社の企業が活用したと推定される。このうち金融円滑化法の終了に伴い支援が必要となる企業は5万社~6万社とみられる。しかし、業績改善が進まず再建計画と大きく乖離している企業や、1年以内に策定しなければならない実抜計画を作成できない企業も多い。金融機関は、再建が見込めない企業には資産売却や廃業も視野に入れた対応をする一方で、企業側も問題点を見直し、業績改善や経営立て直しに改めて取り組まなければならない時期にきている。














