報酬1億円以上の役員 初の300人超
2013年3月期決算の上場企業2,505社のうち、6月30日までに役員報酬1億円以上を開示した企業は175社、人数は301人だった。前年(2012年3月期)より社数で3社(前年172社)、開示人数は6人(同295人)増加した。
役員報酬の最高額は、日産自動車のカルロス ゴーン代表取締役社長兼最高経営責任者が9億8,800万円(前年9億8,700万円)と、2年ぶりに報酬額トップに返り咲いた。また、開示制度が開始されてから4年目を迎え、2010年3月期から4年連続で個別開示行った企業は38社(構成比21.7%)、開示人数は135人(同44.8%)だった。
- 本調査は、2013年3月期決算の全証券取引所の上場企業を対象に、有価証券報告書から役員報酬1億円以上の個別開示を行った企業を集計した。上場区分は2013年6月30日時点。
- 2010年3月31日に施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の改正」で、上場企業は2010年3月期決算から取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)など役職別及び報酬等の種類別の総額を、さらに提出企業と連結子会社の役員としての連結報酬1億円以上を受けた役員情報を有価証券報告書に記載することを義務付けられた。今回の内閣府令改正にあたっては、上場企業の「コーポレート・ガバナンス」(企業統治)に関する開示内容の充実を図ることを目的にしている。
- 各数値は小数第2位を切り捨て。
個別開示対象者301人のうち、233人(構成比77.4%)は提出企業からの報酬だけだった。
301人の役員報酬総額は507億8,100万円(前年521億3,600万円)で、前年より13億5,500万円減少した。役員報酬の主な内訳は、基本報酬が317億2,000万円(構成比62.4%)、賞与が92億3,900万円(同18.1%)、退職慰労金(引当金繰入額含む)が38億8,900万円(同7.6%)だった。
開示人数の最多はファナック(東証1部)の13人だった。前年(14人)より1人減少したが、前年に引き続きの最多開示人数だった。次いで、三菱商事と日産自動車が各6人(前年6人)、大塚ホールディングス(同10人)、武田薬品工業(同3人)、野村ホールディングス(同2人)、大和証券グループ本社(同ゼロ人)が各5人と続く。役員報酬1億円以上が2人以上だった企業は67社(構成比38.2%)で、前年の64社を3社上回った。役員報酬の個別開示があった175社のうち、銀行や変則決算企業を除く171社の業績(単体)は、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前年を上回った企業が63社(構成比36.8%)あった。
役員報酬 日産自動車社長 カルロスゴーン氏が2年ぶりに首位に返り咲く
2013年3月期決算の役員報酬の最高額は、日産自動車のカルロス ゴーン代表取締役社長兼最高経営責任者が9億8,800万円(提出会社だけからの報酬、前年9億8,700万円)。開示制度が開始された2010年3月期以降、2年連続で報酬額トップの座を、2012年3月期に明け渡した。しかし、2013年3月期に再び報酬額トップに返り咲いた。次いで、武田薬品工業のデボラ・ダンサイア取締役が7億7,600万円(提出会社および連結会社からの報酬、同開示対象外)、同社フランク・モリッヒ取締役(チーフコマーシャルオフィサー)が7億6,200万円(同、前年2億6,900万円)、同社山田忠孝取締役(チーフメディカル&サイエンティフィックオフィサー)が7億1,200万円(同、同2億4,900万円)、日本調剤の三津原博代表取締役社長(同、同6億5,100万円)とファナックの稲葉善治代表取締役社長(提出会社のみからの報酬、同5億9,700万円)が5億9,000万円と続く。
上位5位(6人)のうち、3人が武田薬品工業の取締役で、株価上昇に伴いストックオプションの報酬額が増加し、報酬額の50%以上を占めている。
上位10人では、フォーカスシステムズの東光博元相談役のみが退職慰労金が主体の報酬体系で、ほか9人は基本報酬、賞与、ストックオプションを主とした報酬体系であった。また、2年連続で上位10人にランクインしたのは4人だった。
個別開示対象301人のうち、2年連続の開示対象者は218人(構成比72.4%)。このうち、115人が前年より役員報酬額が増加し、減額は82人、同額は21人。新規開示(前年開示なし)は83人だった。また、4年連続で1億円以上の役員報酬を受け取ったのは135人(構成比44.8%)だった。
301人のうち、役員報酬額10億円以上はゼロ人(前年1人)、9億円台は1人(同1人)、8億円台はゼロ人(同1人)、5~7億円台が6人(同6人)、2~4億円台が41人(同48人)、1億円台が253人(同238人)。2億円以上が48人と前年(57人)を下回り、1億円台の構成比が84.0%と前年(80.6%)を3.4ポイント上回った。
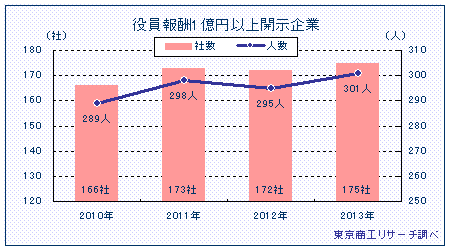
業績に連動した報酬体系へ
301人の役員報酬総額は、507億8,100万円(前年521億3,600万円)だった。役員報酬の主な内訳は、基本報酬が317億2,000万円(構成比62.4%、前年306億6,500万円)、賞与が92億3,900万円(同18.1%、同88億5,100万円)、ストックオプションが44億5,600万円(同8.7%、同32億7,300万円)、退職慰労金(引当金繰入額含む)が38億8,900万円(同7.6%、同78億5,000万円(同15.1%)、業績連動報酬(8億6,800万円)、中期インセンティブ(1億6,600万円)など。役員任期中の安定報酬である基本報酬が主体の報酬体系に大きな変化はないが、業績が反映される賞与やストックオプションが増加した。
上位50位(51人)の役員報酬総額は172億2,300万円。主な報酬内訳では基本報酬95億8,000万円(構成比55.6%)、賞与33億2,500万円(同19.3%)、ストックオプション22億200万円(同12.7%)、退職慰労金(引当金繰入額含む)17億6,600万円(同10.2%)。
上位50位(51人)では、全体に比べ基本報酬が6.8ポイントダウンした一方で、賞与が1.2ポイント、ストックオプションが4.0ポイントアップした。開示制度の開始から4年目になるが、業績に連動した報酬体系に移行しつつあることがうかがわれる。
報酬支払元別 提出会社からの報酬のみが約8割
個別開示対象301人のうち、有価証券報告書を提出した会社のみから役員報酬1億円以上を受け取ったのが233人(構成比77.4%、前年228人)で最多。このほか、提出会社と連結会社の両方から役員報酬を受け取ったのが61人(同20.2%、同57人)、連結会社のみから役員報酬を受けたのが7人(同2.3%、同10人)だった。
上位10人では、報酬の支払元が提出会社のみと提出会社と連結会社で、各5人だった。
法人別 ファナックが2年連続で開示人数が最多
2013年3月期決算で、法人別で役員報酬1億円以上の開示人数が最も多かったのは、ファナックの13人。2012年3月期の14人より1人減少したが、安定した業績を維持し、2年連続で最多の開示人数となった。
以下、三菱商事、日産自動車が各6人、大塚ホールディングス、武田薬品工業、野村ホールディングス、大和証券グループ本社が各5人と続く。グローバル展開をしているメーカー、商社などが上位に並んでいる。また、株価上昇などにより業績が回復した証券会社も、開示人数を増加させた。
開示人数別では、1人の企業が108社(構成比61.7%、前年108社)と最も多く、2人が40社(同22.8%、同42社)、3人が12社(同6.8%、同9社)と続く。複数の役員に対し1億円以上の役員報酬を支払った企業は67社(構成比38.3%)で、2012年3月期64社(同37.3%)より1.0ポイントアップした
個別開示した175社のうち、2年連続で個別開示した企業は139社。このうち、18社は前年より個別開示人数が増加、18社が減少した。同数は103社。一方、前年に個別開示したものの、2013年3月期は個別開示がなかったのは33社。
また、開示制度が開始された2010年3月期から4年連続で個別開示した企業は38社(構成比21.7%)、3年連続は6社だった。
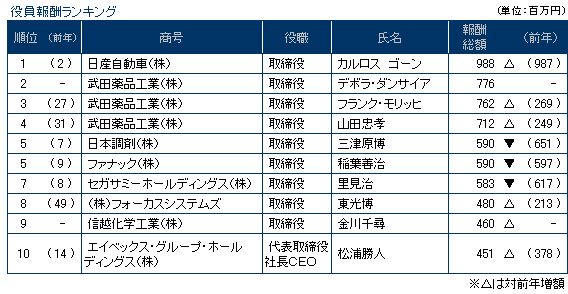
赤字決算、無配で1億円以上の役員報酬開示
赤字決算(単体)で、1億円以上の役員報酬を支払った企業は10社。このうち、フェローテック、東京機械製作所(各2人)の2社が、複数人の役員に1億円以上の役員報酬を支払った。また、無配だったが、1億円以上の役員報酬を支払った企業は4社だった。
赤字決算で、無配ながら、1億円以上の役員報酬の個別開示をした企業は2社で、このうち東京機械製作所が唯一、複数人の個別開示を行った。東京機械製作所は、2013年3月期決算で、4期連続で営業損失になったことなどから、継続企業の前提に関する事項が注記された。
産業別 製造業が87社・148人で最多
役員報酬1億円以上の個別開示を産業別でみると、製造業が87社(構成比49.7%、前年91社)・148人(同49.1%、同151人)と最も多かった。次いで、サービス業他(持ち株会社を含む)が43社(同24.5%、同34社)・81人(同26.9%、同67人)、卸売業が15社(同8.5%、同20社)・29人(同9.6%、同38人)と続く。
一方、農・林・漁・鉱業では役員報酬の個別開示は3年連続で該当者はいなかった。
個別開示社数・対象人数が増加したサービス業他では、株価の上昇などもあって業績が回復した証券・銀行・保険などの金融関連の持ち株会社などで開示人数が増加した。主だった企業では、大和証券グループ本社が0人→5人(5人増)、野村ホールディングスが2人→5人(3人増)、三菱UFJフィナンシャル・グループが2人→4人(2人増)、みずほフィナンシャルグループが0人→2人(2人増、3年ぶりの個別開示)、東京海上ホールディングスが0人→1人(1人増)、岡三証券グループが0人→1人、東海東京フィナンシャル・ホールディングス0人→1人(1人増、初開示)。
市場別 東証1部が143社・263人で8割以上
個別開示のあった企業を市場別(東証及び大証の両市場に上場している場合は東証でカウント)にみると、東証1部が143社(構成比81.7%、前年140社)・263人(同87.3%、同254人)で、ともに8割以上を占めた。次いで、JASDAQが18社(同10.2%、同22社)・23人(同7.6%、同30人)、東証2部が10社(同5.7%、同6社)・10人(同3.3%、同6人)、大証などの地方上場が4社(同2.2%、同4社)・5人(同1.6%、同5人)の順だった。
社数・人数がともに最多だった東証1部は、グローバル企業も多く、国内だけでなく海外にも事業基盤を構築している。対象的に、新興市場は設立の浅い企業が多く、内部留保の充実や設備投資などへ資金投下を優先させるなど事業基盤の強化を図っているために開示社数・人数が少なかった。
業歴別 業歴50年以上が6割
個別開示のあった企業を業歴別でみると、50年以上100年未満が110社(構成比62.8%、前年105社)・194人(同64.4%、同178人)、100年以上が6社(同3.4%、同6社)・11人(同3.6%、同11人)。業歴50年以上の個別開示は116社(同66.2%、同111社)・205人(同68.1%、同189人)で、全体の6割以上を占めた。一方、10年未満は8社(同4.5%、同9社)・16人(同5.3%、同23人)。業歴の長い企業は相応の事業基盤が構築されている一方で、業歴の浅い企業は事業基盤の形成途上にあって、個別開示社数・人数に差が生じた。
従業員平均給与 平均1,000万円台が開示人数が最多
個別開示のあった企業の従業員平均給与をみると、社数では600万円台が45社(構成比25.7%、前年42社)で最多。次いで、前年最も多かった700万円台は32社(同18.2%、同46社)、500万円台が31社(同17.7%、同23社)と続く。開示人数では、1,000万円以上が70人(同23.2%、同77人)と最多。次いで、600万円台が65人(同21.5%、同56人)、700万円台が50人(同16.6%、同69人)と続く。従業員の平均給与1,000万円以上の企業では、個別開示の人数が最も多く、従業員にも相応の給与が支払われていることがうかがわれる。
2013年3月期決算は、2012年12月頃から円安・株価上昇などにより、決算の改善に大きく寄与し、役員報酬の個別開示の制度が開始されてから初めて開示人数が300人を超えた。また、賞与やストックオプションなどが報酬に占める割合が上昇するなど、業績に連動した報酬体系に移行しつつある。
役員報酬額は、「経営方針」「業績」「配当」「長年の実績(会社への貢献度)」など、様々な基準で報酬額の妥当性が判断される。4年目を迎えた役員報酬の個別開示制度は多くの人に認知されるようになった。しかし、上場企業に限らず、年々、「コーポレートガバナンス」や「コンプライアンス」に対しシビアになっていて、役員報酬は基準の一つとなっている。そのため、一段と株主や従業員、金融機関、取引先などステークホルダー(利害関係者)への説明責任が求められてくることが予想される。














