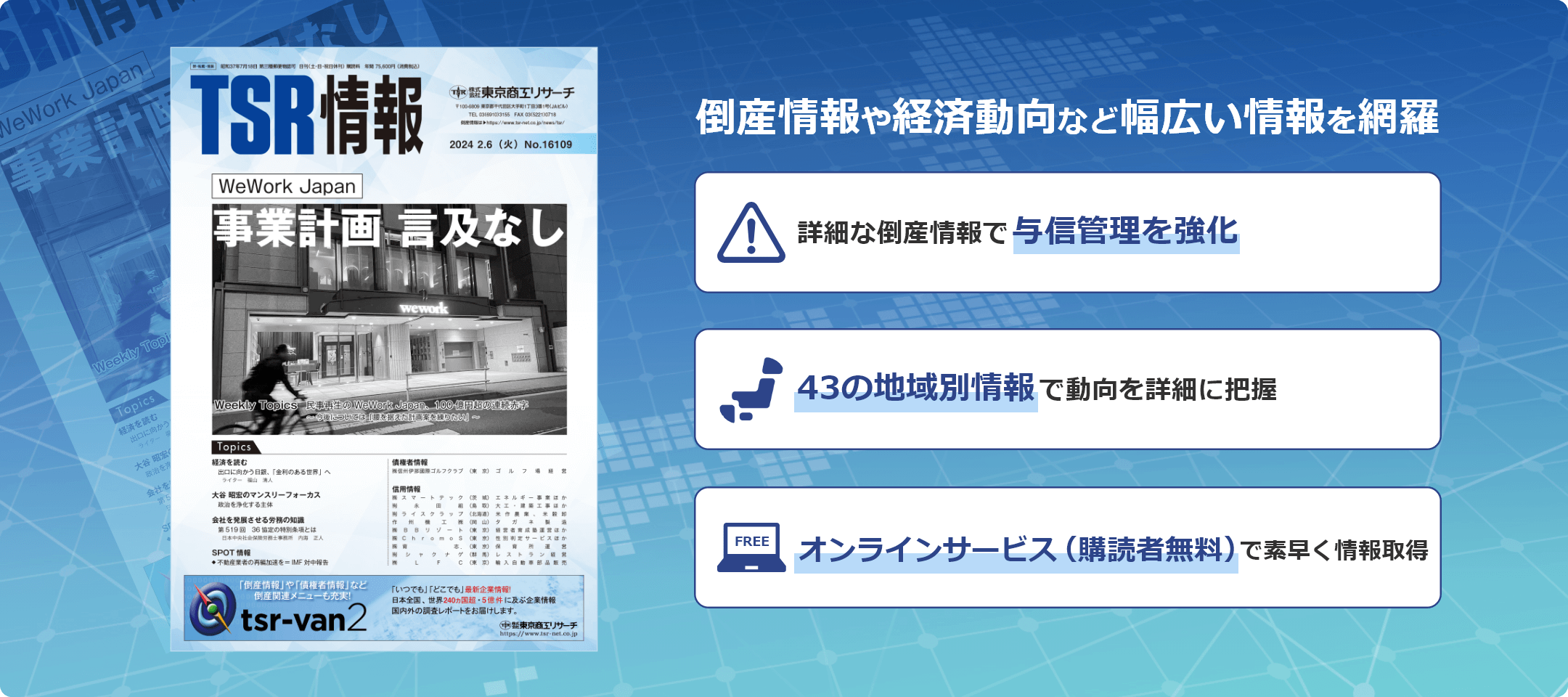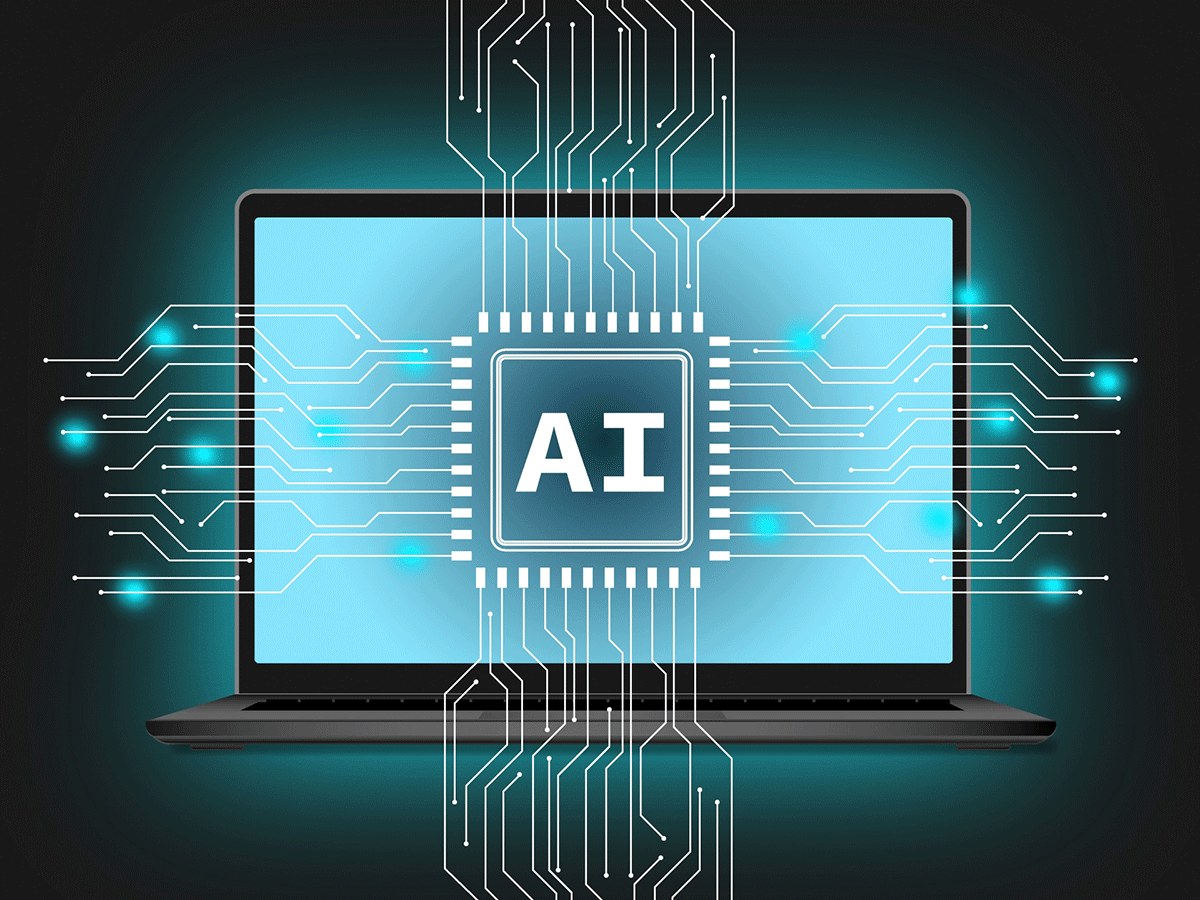東北経済産業局・佐竹佳典局長インタビュー ~半導体産業が起爆剤 雇用とにぎわい創出へ~ 2024/12/18
2024年7月に東北経済産業局長に就任した佐竹佳典氏は「半導体産業を起爆剤に、地域の魅力をアピールして人口減少に歯止めをかけたい」と話す。東北経済産業局では他省庁や民間の専門家と連携し、地域裨益の最大化へ繋げることを目的に“「半導体well-being」な街-研究会”を今夏に立ち上げ、自治体のサポートに注力している。
東京商工リサーチ(TSR)は、佐竹局長に東北地方の産業の分析、物価高や事業承継などを聞いた。
―東北地方の産業の強みについて
私は山形市出身で、入省当初の4年間はこの東北経済産業局(当時は仙台通商産業局)に所属しており、今回ご縁があって30数年ぶりに東北の地に戻ってきた。本省では、エネルギー政策や産業政策に関して日本全国の情勢を俯瞰する必要があり、在外勤務の時は世界から見た日本というマクロの視点が求められた。東北という特定の土地にフォーカスして政策を行うのは本当に久しぶりだ。
東北地方は非常にポテンシャルが高い地域だと昔から認識されている。特に半導体や電子部品の出荷額合計は約3.1兆円で全国シェアも高い。政府全体としても半導体が重要物資であると指定しており、予算を組んで、投資を呼び込もうとしている。
1980年代からのインテリジェント・コスモス構想(東北地方の産学官が一体となった未来産業社会の構想)に端を発し、半導体に関連する集積もかなり進んでいる。また、トヨタ自動車東日本(株)の工場などもあり、半導体と自動車の関係がここまで集積しているのは国内では東北地方と九州地方だけだ。
今は全国的に産業用地が不足していて、東北地方でも新しく造成する動きが出ている。半導体産業には大きな土地、電力、水が必要だ。仙台北部中核工業団地はその全てが揃っており、私個人としても大きな可能性を感じている。宮城県と岩手県南部の一関市や北上市は研究開発型企業が多く立地しており、秋田県では洋上風力発電が盛んだ。福島県では水素などを活用した再生可能エネルギーの取り組みが行われ、南部の白河市や郡山市は医療機器産業が集積している。東北名産の水産加工品・農産品も大変魅力的だ。
―国内の半導体産業の現状は
半導体産業は、大別すると半導体チップと半導体製造装置に分けられる。半導体チップの中でもフラッシュメモリーに関しては岩手県北上市に製造拠点を持つキオクシア(株)と、連携企業の米国ウエスタンデジタルがある程度の世界的シェアを持っている。シリコンウエハ関係は日本が世界のトップのような形になっており、パワー半導体も日本勢が貢献している。半導体製造装置は東京エレクトロン(株)が大きい。
東北地方では先日、台湾の力晶積成電子製造(PSMC)が宮城県での半導体工場の建設計画から撤退した。しかし、それがなくても半導体関連の事業所の立地・増床は、今後は約1.2兆円の投資が計画されている。首都圏から仙台市まで新幹線でわずか1時間半なので、企業立地も今後どんどん見込まれる地域ではないか。
半導体産業を起爆剤としていくためには、同時に商業施設や道路などをしっかり整備することで、地域の魅力をアピールすることも必要だ。東北地方の人口は減少傾向にあり、特に若者や女性の首都圏への流出が問題視されている。歯止めをかけるためにも良質な雇用を確保して、生活インフラを整えなくてはならない。そういった考えの下、2024年8月に“「半導体well-being」な街-研究会”を立ち上げた。

東北経済産業局・佐竹佳典局長
―“「半導体well-being」な街-研究会”の取り組みは
東北経済産業局・宮城県・岩手県の共催で、半導体関連企業が立地または近接している自治体向けにさまざまな情報共有等を行い、産官学金が連携しながら地域裨益の最大化へ繋げることを目的としている。東北地方整備局、東北運輸局、中小企業基盤整備機構東北本部などの協力を得ながら、「商業誘致」「産業創出」「都市計画」「DX・定住」の4分野の専門家を招き、「地域の交通網はどのように整備するのがいいか」「商業施設はどういうやり方がいいのか」などの具体的な事例、施策紹介等を行っている。
半導体産業の商流では、ファブレス(設計企業)が回路図を制作し、ファウンドリー(受託製造企業)が量産体制を構築する。東北地方にはファブレスが少ないという課題があるので、東北大学を中心として人材育成に取り組み、知識集約的な産業を育てていかなくてはならない。
研究会ではベンチャー企業の支援も含め、良質な雇用をしっかり確保して、人材にこの地域に残ってもらえるよう方策を話し合っている。Indeedによる「半導体に関する仕事の検索動向調査」の結果を見ると、半導体関連の仕事検索は熊本県であれば全国から閲覧がある一方で、宮城県など東北地方の仕事検索は西日本からはほぼ閲覧がなく、知名度に欠けている。良質な雇用があり、非常に住みやすい土地であることを周知するためにも、研究会でしっかりステークホルダーも巻き込みながらPRして、地域全体の発展につなげていきたい。他省庁や民間の専門家と連携しながら、これほど広域でかつ幅広い分野を扱う研究会を立ち上げるのはおそらく全国的にも初めての試みだろう。
―次世代放射光施設「NanoTerasu(ナノテラス)」の地元企業の利用促進・事業活用について
地元の中小企業が新しいイノベーションや新しいビジネスにつなげている事例がかなりみられるようになっている。ナノテラスを利用するきっかけは公設試験研究機関(公設試)の紹介が多いようだ。地域の中小企業や中堅企業がナノテラスを有効に活用して研究開発していくためには、仲介する役割が必要になるので、そういった利用促進のプラットフォーム構築のために、我々も公設試や研究機関とつながりを強化している。
東北経済産業局では企業経営層向けの「観えると変わるものづくりの未来;ものづくり中小企業に伝えたい放射光利活用のメリット(放射光利活用事例集)」を制作し、2023年7月からHP上で公開している。
例えば、日本酒の地理的表示(GI)についてナノテラスで成分を分析して、従来は経験値だった企業ノウハウを数値データとして標準化することも可能だ。正しい技術継承や新しい技術革新にもつながっていくので、ナノテラスの利用を我々も積極的にPRして、ご相談があればつなげていきたい。
―物価高、人手不足など東北地方の企業が抱える問題について
政府としても人手不足対策と賃上げについては力を入れている。賃上げ原資確保のための価格転嫁は事業者によって二極化されているのが現状で、BtoBに関しては大手企業及びティア1・ティア2の中堅企業はある程度転嫁ができているようだ。サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるため、経産省全体としても、引き続き環境整備や公正取引委員会との連携による法執行強化を行っていく方針だ。
一方で、BtoCの飲食業や小売業などは、売上への影響を考えると、なかなか販売価格の値上げは難しいとの声も聞かれる。地域の飲食店経営者には「安くておいしいものを消費者に提供したい」というマインドがあるはずだ。消費者側としても今後、単純に安さだけではなく「価値あるものに対して、見合う対価を支払う」という意識が広がっていくべきだろう。良い商品を提供する企業にしっかりと稼いでいただくことで、新しいお店が出てきたり、トライしたいという企業も増え、後継者不足の対策としても大事になってくるだろう。
―事業承継が進まず、倒産の前段階で休業・廃業に至るケースもある
事業承継は東北地方において大きな課題であると東北経済産業局としても認識している。関係機関と連携して話し合う機会もあるが、行きつくのは人材が一番大事だということ。事業承継も含めて、新しいことを生み出したり、新しいビジネスをスタートするには、やはり人の力が必要だ。
東北地方で特に特徴的な課題は人口減少だろう。地域の若者が都市部に流れており、中でも女性の流出は顕著だ。経産省では、中小企業の売上高「100億円企業」への成長を目指して各種支援策の検討を始めているほか、中堅企業向けには税制面などでサポートする方針を打ち出しており、これらは地方に良質な雇用を生み出す狙いもある。首都圏のほうが仕事の選択肢も多く、賃金基準が高いのは事実だが、地方にはワークライフバランスの取りやすさ、子育てのしやすさなど利点もあることをPRする必要がある。
―2024年11月、東北大学が国際卓越研究大学に認定された
産業全体の発展を考えた時に県単位で区切った政策は小規模なものにとどまってしまう。そこで我々としては東北大学の役割に注目している。スタートアップや外国人就労に関するプラットフォームも東北大学が主導し、宮城県だけではなく東北地方全体を俯瞰しながら進めていく流れになっている。
プロジェクトベースで積み重ねて、プラットフォームを拡大していくのが経産省の地方支分部局である我々のミッションであると考えている。東北全体を広く見ると同時に、現場の声もきちんと聞かなくてはならない。「虫の目と鳥の目」「マクロとミクロ」の広い視点を持って問題を見てほしいということは、東北経済産業局の職員には常々伝えている。
―洋上風力発電など再生可能エネルギーのポテンシャルは
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、東北でも様々なプロジェクトが形成されている。その中で、例えば水素や洋上風力発電などの再生可能エネルギーの取り組みがあるが、いかに利益を地元企業に還元していくのかという視点も非常に大切だ。東北地方では秋田県が全国に先駆けて洋上風力発電の立地を進めており、民間事業者が主体となって「秋田風作戦」というコンソーシアムを組み、風力関連産業への参入実績などが生まれている。
洋上風力発電の場合は海外メーカーがコア技術を持っているため、地元企業の参入のハードルは高いが、地元の建設会社がメンテナンスに携わるなど体制づくりを行い、地域にもきちんと裨益できるよう取り組んでいる。今後、他地域でも再生可能エネルギーへの投資が進んでいくと思うが、良質な雇用を確保し、人口流出を食い止めるような地域政策となるように取り組んでいくことが重要だ。
2024/12/18
「最新記事」一覧を見る