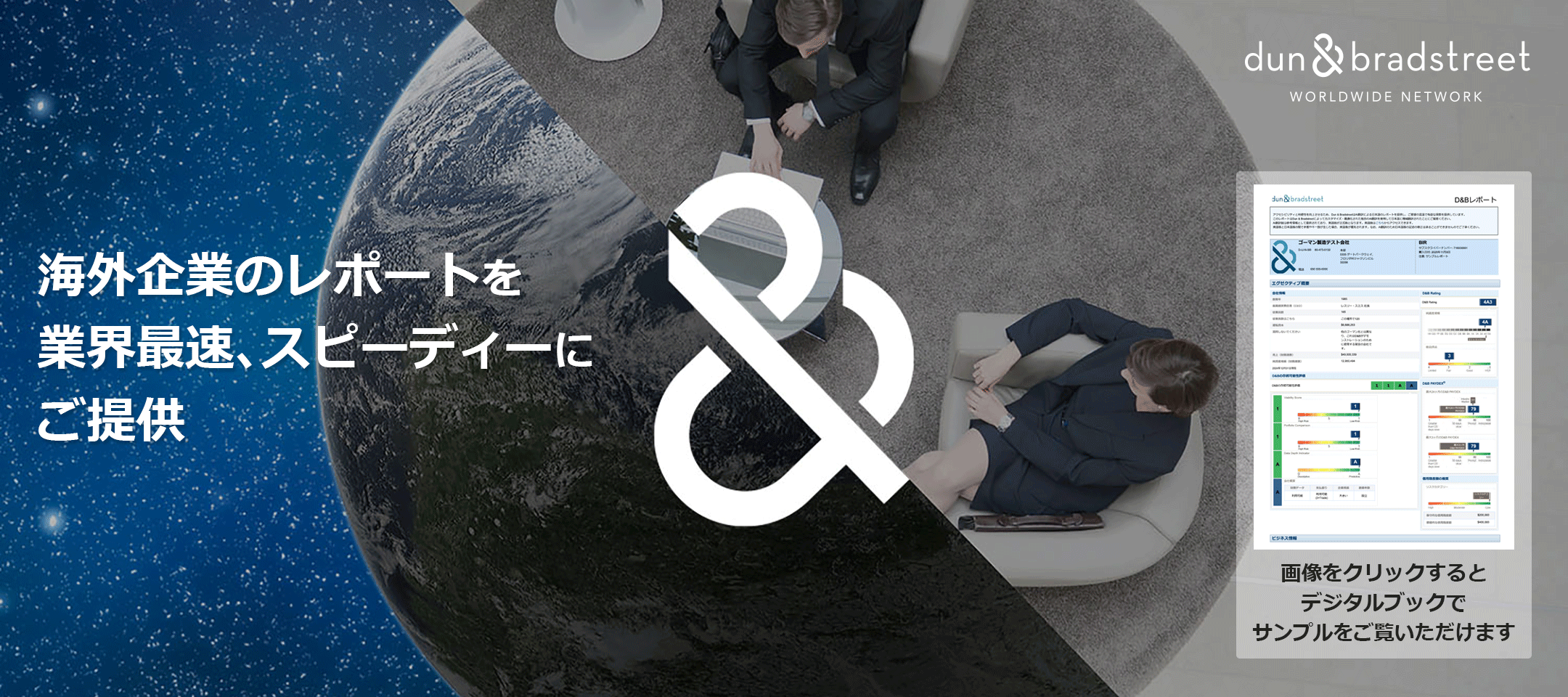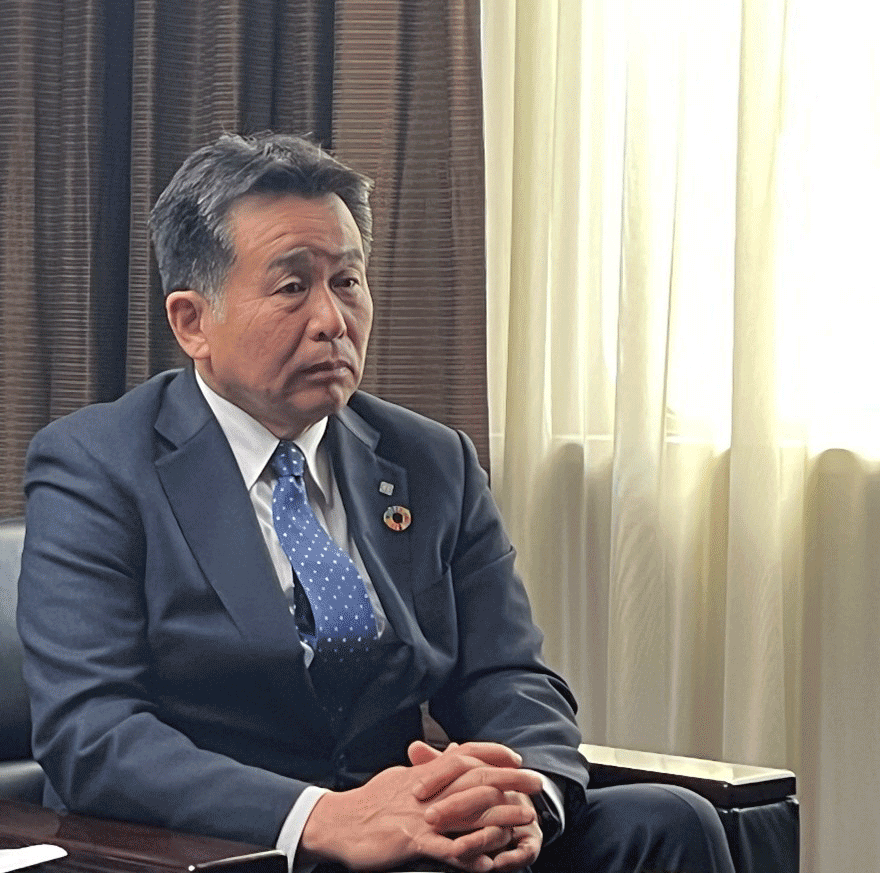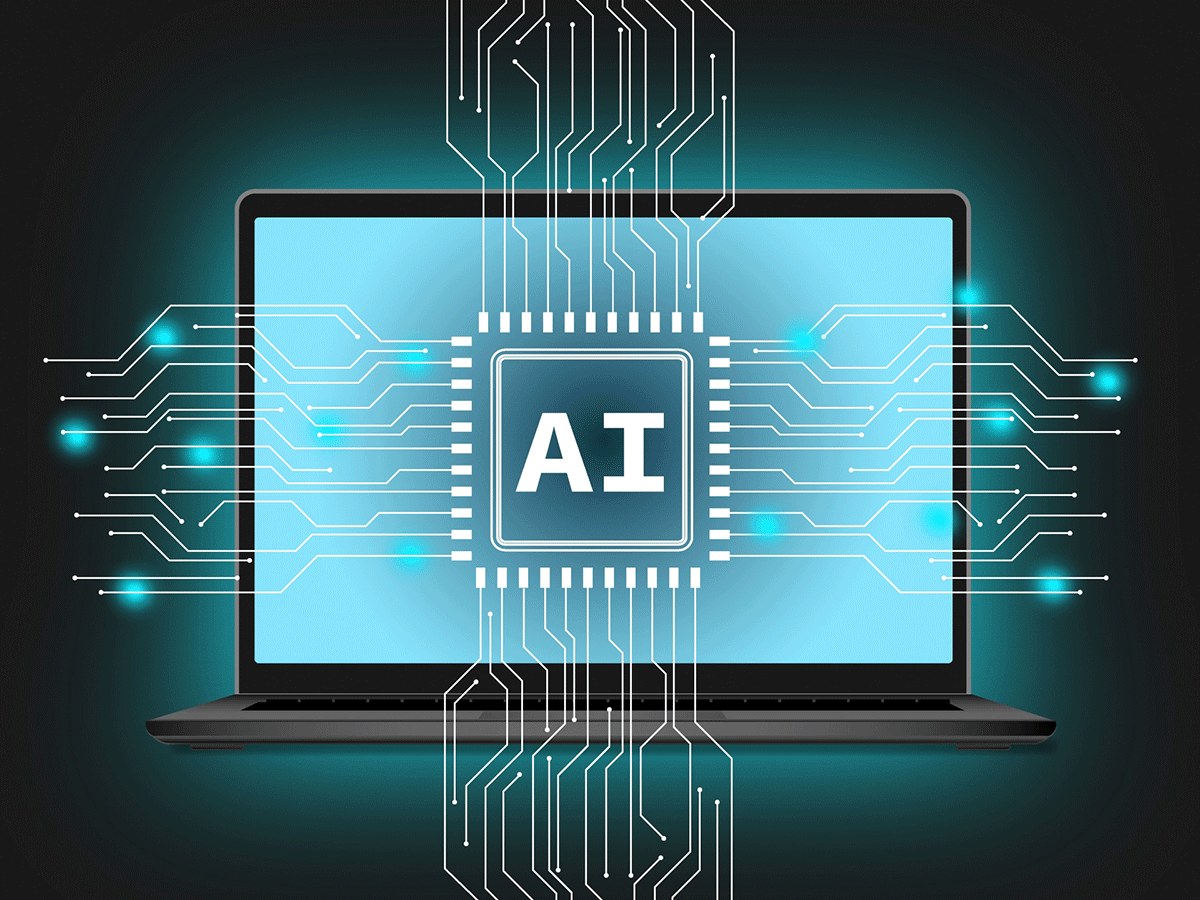収集した情報の整理・評価

収集した情報項目を評価してゆくにあたり、その属性をきちんと見極めておく必要があります。データに一貫性を持たせ、時間が経過してもその評価価値が変動しないようにするためです。(1)定性データと定量データを分ける(2)絶対評価と相対評価を知る(3)経営評価の目的を策定する(4)取引先数に応じた与信方法を決める、と具体的に落とし込む方法を例として挙げたいと思います。
評価の具体例
(1)定性データと定量データ
■定量データ
定量データ(定量情報)とは、数値で表されたデータのことであり、決算書上の情報や評点、リスクスコアなどがあてはまります。企業が公表している数値の多くが、定量データにあたり、数値自体が直接、企業の状態を表します。
■定性データ
定性データとは数値では表せない情報のことであり、概況や事業見通し、経営者の人物像、資金繰り見通しなどがあてはまります。定性データはそのままでは、比較や分析が難しいため、一定のルールを以って数値に置き換えることで、定量データと同様の扱いができます。
定量データと定性データの2つのデータを組み合わせることで、正確な評価を行うことができます。
(2)絶対評価と相対評価
評価方法には絶対評価と相対評価の2種類があります。
絶対評価は地域や業種・規模・年代に左右されない1つの基準によって評価するもので、地域差・業種差・規模による差・年代による変化が評価できる長所を持ちます。
相対評価は集合内における優劣・順位付けを目的とした評価方法であり、そのランキングには説得力があります。しかし、違う集合とは比較できないという難点があります。
(3)経営評価の目的
経営評価はさまざまな業種の企業で数多く実施されています。使用するデータ・評価方法・手段には共通性が多々あります。しかし評価の目的はそれぞれ異なることから評価対象項目・採点基準・評価基準はそれぞれ異なっています。例えば、格付け会社は債権の償還力を評価し、金融機関は融資の可否・返済能力を評価しています。一般企業は取引の可否・支払い能力を判断するために評価し、信用調査会社はさまざまな利用目的を持つユーザーに対応して経営内容の全般を評価・格付けしています。
(4)自動与信評価と手動与信評価
自動与信評価とはコンピューターを駆使して大量のデータを一括して分析・評価するもので、定量データや概略の情報による一次評価に適しており、小口取引先の与信管理向きの手法と云えます。
手動与信評価は詳細データを使用しての手作業・人的判断による手法で、大口・重要取引先の評価や2次・最終判断での利用に適しています。
評価結果は1つの点数や格付けでどちらも同じに見えますが、作成工程は全く異なるため評価対象と目的によって使い分ける必要があります。
年度毎の優良取引先をベースとして、他社の評価項目を決めるなど、業種や状況によって重きを置くポイントは違います。しかしベンチマークするものがなければ作れないというわけではなく、まずは独自の裁量で各入手項目に配点をし、継続的に見直していくことが必要です。