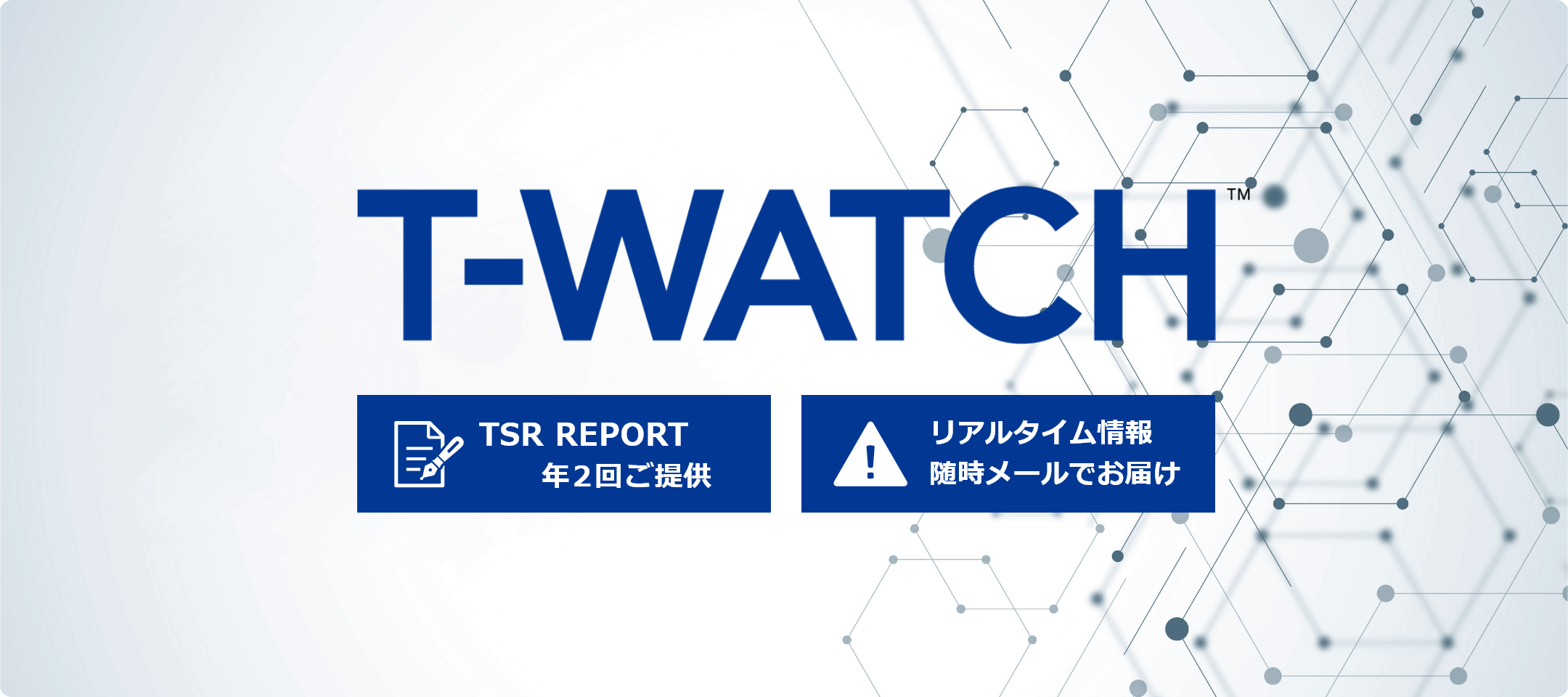全国企業倒産状況
2009年度(平成21年度)[2009.4-2010.3] 全国企業倒産状況
| 倒産件数 | 14,732件 |
|---|---|
| 負債総額 | 7兆1,367億500万円 |
| 対前年度比(件数) | -8.7%(前年度 16,146件) |
| 対前年度比(負債) | -49.0%(前年度 14,018,911百万円) |
(負債総額1,000万円以上の倒産を集計、%は小数点2位以下切捨)
倒産件数が前年度比8.7%減の1万4,732件、「不況型」倒産構成比が過去最高
2009年度(2009年4月~2010年3月)全国企業倒産件数は、1万4,732件、負債総額は7兆1,367億500万円となった。
倒産件数は、前年度比8.7%減(1,414件減)で4年ぶりに前年を下回り、年度としては戦後22番目となった。また都道府県別では、38都道府県で前年を下回り、全国的に倒産が減少した。
これは「景気対応緊急保証制度」や政府系金融機関の低利融資「セーフティネット貸付」、さらに「中小企業等金融円滑化法」施行などの政策が効果を発揮したとみられる。
負債総額は、前年度比49.0%減(6兆8,822億600万円減)となり、年度としては戦後14番目の規模だった。負債100億円以上が同55.9%減の59件(前年度134件)と大幅に減少したことが影響した。
産業別
倒産件数、10産業のうち8産業で前年度比減少
前年度比減少率は、金融・保険業の28.9%減(107→76件)を筆頭にして、卸売業14.7%減(2,315→1,974件)、運輸業14.3%減(635→544件)、不動産業14.2%減(625→536件)、建設業14.1%減(4,540→3,898件)、小売業11.7%減(1,839→1,623件)、農・林・漁・鉱業6.9%減(86→80件)、製造業5.5%減(2,540→2,400件)の順。
これに対して増加は、情報通信業6.7%増(559→597件)とサービス業他3.5%増(2,900→3,004件)の2産業だった。
| 産業別分類 | 件数(件) | 負債額(百万円) |
|---|---|---|
| 農・林・漁・鉱業 | 80 | 26,106 |
| 建設業 | 3,898 | 723,582 |
| 製造業 | 2,400 | 778,190 |
| 卸売業 | 1,974 | 559,030 |
| 小売業 | 1,623 | 196,729 |
| 金融・保険業 | 76 | 378,149 |
| 不動産業 | 536 | 826,923 |
| 運輸業 | 544 | 1,680,152 |
| 情報通信業 | 597 | 311,253 |
| サービス業他 | 3,004 | 1,656,591 |
| 合計 | 14,732 | 7,136,705 |
※業種分類のコード(日本標準産業分類に基づく)改訂に伴い、弊社データベースは2009年1月度より新業種分類に移行した。各数値は新業種コードに基づく。
地区別
倒産件数では9地区のうち近畿を除く8地区で前年度を下回った。
減少率は、北海道34.0%減(741→489件)、九州26.8%減(1,435→1,050件)、中国24.5%減(765→577件) 、東北23.2%減(896→688件)、四国20.3%減(452→360件)、北陸9.5%減(451→408件)、関東5.0%減(5,782→5,489件)、中部0.6%減(1,631→1,621件)の順。これに対して増加は、近畿の1.4%増(3,993→4,050件)だけだった。
また都道府県別倒産件数では、前年同月を下回ったのが38都道府県、増加が9府県となった。
- 北海道:年度としては19年ぶりに500件を下回る。
- 東北:年度としては18年ぶりに700件を下回る。県別件数では、全県で前年度比減少。
- 関東:全体の件数が、前年度比5.0%減。県別件数では、千葉、神奈川で前年度比増加。
- 中部北陸:全体の件数が、中部が前年度比0.6%減、北陸が同9.5%減。県別件数では、愛知、三重、富山で前年度比増加。
- 近畿:年度としては7年ぶりに4,000件台に増加した。県別件数では、滋賀、大阪、和歌山で前年度比増加。
- 中国:年度としては5年ぶりに600件を下回る。県別件数では、全県で前年度比減少。
- 四国:全体の件数が、前年度比20.3%減。県別件数では、全県で前年度比減少。
- 九州:年度としては19年ぶりに1,100件を下回る。県別件数では、全県で前年度比減少。
| 地区別分類 | 件数(件) | 負債額(百万円) |
|---|---|---|
| 北海道 | 489 | 177,113 |
| 東北 | 688 | 161,601 |
| 青森 | 96 | 23,462 |
| 岩手 | 91 | 39,171 |
| 宮城 | 171 | 36,486 |
| 秋田 | 90 | 14,787 |
| 山形 | 95 | 14,338 |
| 福島 | 145 | 33,357 |
| 関東 | 5,489 | 4,456,304 |
| 茨城 | 238 | 84,660 |
| 栃木 | 153 | 50,384 |
| 群馬 | 173 | 89,333 |
| 埼玉 | 615 | 139,923 |
| 千葉 | 436 | 134,217 |
| 東京 | 2,867 | 3,722,702 |
| 神奈川 | 795 | 169,148 |
| 新潟 | 131 | 30,959 |
| 山梨 | 81 | 34,978 |
| 中部 | 1,621 | 459,393 |
| 長野 | 192 | 92,312 |
| 岐阜 | 205 | 48,619 |
| 静岡 | 286 | 96,610 |
| 愛知 | 798 | 193,711 |
| 三重 | 140 | 28,141 |
| 北陸 | 408 | 132,928 |
| 富山 | 147 | 48,591 |
| 石川 | 161 | 58,804 |
| 福井 | 100 | 25,533 |
| 近畿 | 4,050 | 1,044,139 |
| 滋賀 | 204 | 30,813 |
| 京都 | 523 | 87,952 |
| 大阪 | 2,296 | 735,571 |
| 兵庫 | 713 | 154,704 |
| 奈良 | 158 | 22,183 |
| 和歌山 | 156 | 12,916 |
| 中国 | 577 | 190,230 |
| 鳥取 | 48 | 18,415 |
| 島根 | 64 | 13,959 |
| 岡山 | 143 | 55,240 |
| 広島 | 224 | 74,088 |
| 山口 | 98 | 28,528 |
| 四国 | 360 | 256,019 |
| 徳島 | 52 | 10,888 |
| 香川 | 122 | 206,018 |
| 愛媛 | 117 | 19,150 |
| 高知 | 69 | 19,963 |
| 九州 | 1,050 | 258,978 |
| 福岡 | 451 | 114,734 |
| 佐賀 | 60 | 15,722 |
| 長崎 | 121 | 29,521 |
| 熊本 | 127 | 22,948 |
| 大分 | 84 | 17,283 |
| 宮崎 | 74 | 16,913 |
| 鹿児島 | 72 | 24,204 |
| 沖縄 | 61 | 17,653 |
| 合計 | 14,732 | 7,136,705 |
- ※地区の範囲は以下に定義している。
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨)
中部(長野、岐阜、静岡、愛知、三重)
北陸(富山、石川、福井)
近畿(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
- 「不況型」倒産構成比が年度過去最高の80.7%
- 形態別:破産が年度過去最多の9,964件
- 負債額別:100億円以上の大型倒産が前年度比55.9%減の59件(前年度134件)
- 従業員数別:5人未満の構成比が年度としては平成2番目に高率の63.1%
- 従業員被害状況:前年度比24.4%減の13万人
- 中小企業倒産(中小企業基本法に基づく)は、前年度比8.6%減の1万4,646件
当年の主な倒産
- (株)日本航空インターナショナル/東京都/旅客運送事業、貨物事業/1,527,919百万円/会社更生法
- (株)日本航空/東京都/持株会社/671,578百万円/会社更生法
- (株)ロプロ/大阪府/貸金業/250,034百万円/会社更生法
- (株)ウィルコム/東京都/PHSデータ通信業/206,000百万円/会社更生法
- (株)ジョイント・コーポレーション/東京都/不動産分譲、流動化事業/147,600百万円/会社更生法
禁・転載・複写