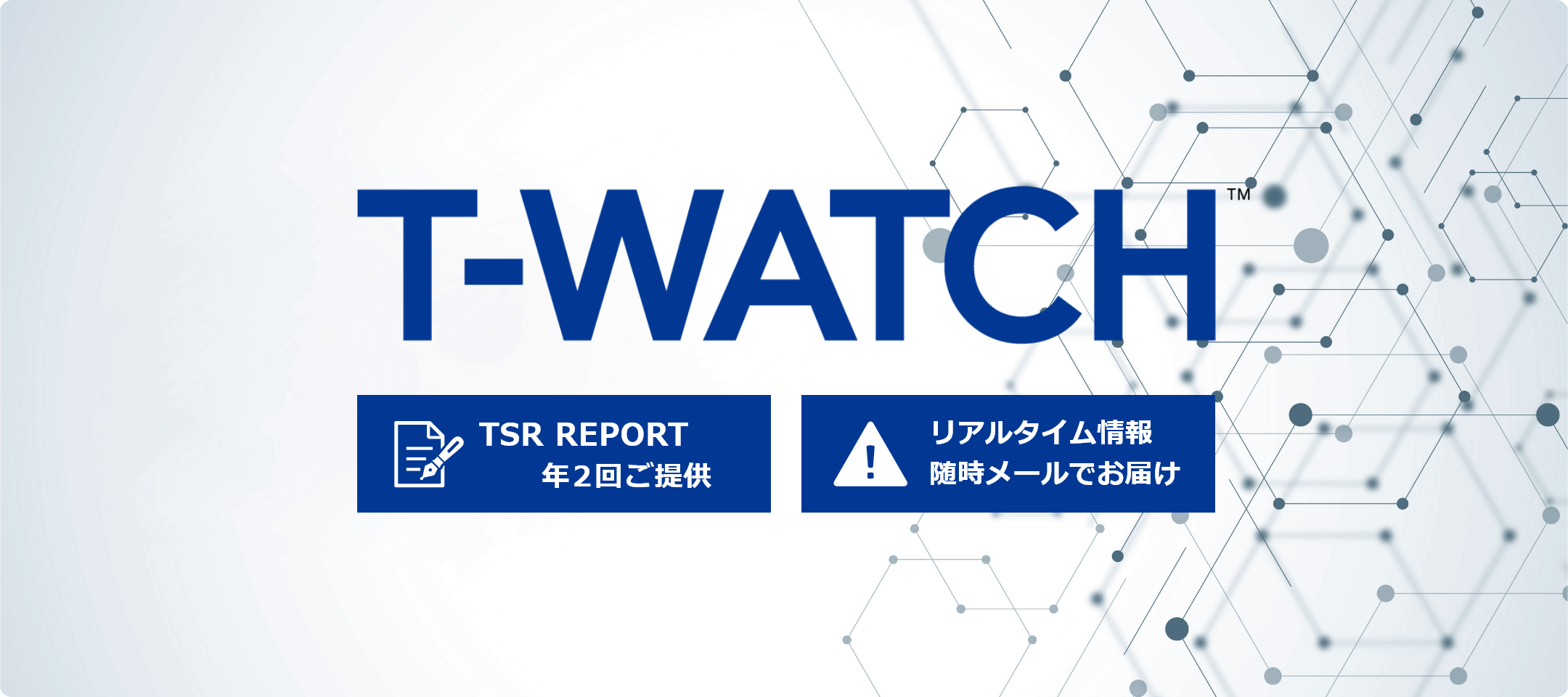土地興業(株)(新宿区袋町3、設立大正8年10月、資本金19億2000万円、上杉定嗣社長、従業員19名)は5月11日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。申立代理人は大宮立弁護士(千代田区丸の内1−6−5、電話03−5220−1861)ほか。負債は約320億円。
同社は大正8年10月に設立された不動産業者。昭和16年から(株)熊谷組(東証1部、新宿区)との関係を強化。その後、ゴルフ場運営、会員権売買、マンション分譲など不動産関連事業を順次拡大し、バブル期には和歌山・三重県などに、関連会社を通じてゴルフ場経営を行うほか、マンション、ニュータウンなどの分譲、海外展開なども行い、平成5年3月期には年商89億4900万円を計上。また、(株)熊谷組の筆頭株主(平成18年3月期末時点で9.53%)となっていた。
しかし、バブル崩壊後の不動産価格の下落から多額の含み損が発生。以降は保有不動産の売却や関連会社の整理を進めていたため、長年に渡って特別損失による赤字を計上。平成18年3月期には年商38億300万円に対して84億7700万円の当期損失となり253億1200万円の債務超過に陥っていた。
なお、(株)熊谷組では「本申立に伴う当社の平成20年3月期の連結業績に与える影響は軽微」としている。

(株)サニーフィールドゴルフ倶楽部(常陸大宮市野口1743−14、登記上:東京都港区西麻布3−14−26、設立昭和58年7月、資本金1億1000万円、佐藤友久社長、従業員2名)と関連会社の(株)エス・エフ・ジー(同所、設立平成10年4月、資本金1000万円、岡本隆社長、従業員40名)の両社は5月14日、東京地裁へ民事再生手続開始を申し立て同日保全命令を受けた。
申立代理人は野中信敬弁護士(東京都千代田区神田紀尾井町3−20、電話03−3288−5228)ほか。監督委員には岡正晶弁護士(千代田区丸の内2−4−1、電話03−3212−1451)が選任されている。負債はサニーフィールドゴルフ倶楽部が約170億円、エス・エフ・ジーが約1億8000万円。
サニーフィールドゴルフ倶楽部は昭和58年7月に設立されたゴルフ場経営会社。昭和62年7月に「サニーフィールドゴルフ倶楽部」をオープン。同ゴルフ場は18ホール、パー72、7030ヤード、130万平方メートルの丘陵コースで、折からのバブル景気に乗り順調にスタートしたが、バブル崩壊後は業績が低迷。そのため、平成9年に到来した預託金の償還が出来ず10年間の延長で凌ぐとともに、平成10年4月に設立したエス・エフ・ジーにゴルフ場の運営を委託した。
しかし、エス・エフ・ジーは年商約5億円で推移、サニーフィールドゴルフ倶楽部はゴルフ場資産の賃貸収入で年間1億8000万円にとどまるなど業績の低迷が続いていた。そうした中、平成18年に合同委員会を組織して再建策を模索していたが、平成19年7月に迎える延長後の預託金償還は難しく、自力再建が困難な状況から民事再生法による再建を図ることとなった。

(株)アーバンフーズ(新宿区大久保2−4−12、設立平成2年4月、資本金2500万円、柳楽光雄社長、従業員41名)は5月28日、東京地裁に破産手続開始を申し立て、同日開始決定を受けた。負債は約91億6300万円。
同社は平成2年4月に設立。その後、休眠状態を経て平成5年10月に現体制となった。当初は食肉加工品を中心に商品開発、販売を行っていたがその後水産加工品、冷凍食品分野にも進出。食肉、水産加工食品をはじめ、餃子、シュウマイなどの冷凍食品まで扱い品は多岐にわたり、商品の企画、開発から食材輸入、商品販売までを手掛け、全国の生活協同組合、食品商社などに販路を築き業容を拡大、平成18年7月期には過去最高となる年商120億5700万円をあげていた。
ところが、今年4月に取引先の1社である大手冷凍食品メーカーの(株)加ト吉(観音寺市、東証1部)グループを中心とした循環取引が発覚、同社も一連の取引に関与していたとされ信用不安が拡大した。同社の不正取引額は年間約50億円にのぼっていたとされ、今回の循環取引問題の発覚以降、商品の仕入れが困難な状況となった事に加え、取引金融機関が態度を硬化、事業継続を断念した。

釜屋化学工業(株)(台東区浅草橋5−23−6、設立昭和18年4月、資本金2億5000万円、小室裕一社長、従業員306名)は5月24日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。申立代理人は松井勝弁護士(中央区京橋2−5−1、電話03−3562−6480)ほか5名。監督委員人には木下秀三弁護士(千代田区五番町10、電話03−3237−1556)が選任されている。負債は約85億9000万円。
同社は明治39年11月の創業、昭和18年に法人化した老舗の合成樹脂成型業者。化粧品を始め薬品、食品などの容器を製造、製造拠点を茨城県古河市と奈良県大和郡山市に設置するほかタイにも現地法人を設立、国内大手化粧品メーカーを中心に海外化粧品メーカー、日本の現地法人などを対象に、ピーク時の平成4年9月期には年商213億1000万円をあげていた。
しかし、近年は得意先の生産拠点海外シフトの影響で売上が低迷、平成19年3月期は年商108億円まで低下していたうえ、原材料の高騰、同業との価格競争で収益面が悪化、過去の積極的な設備投資による借入負担が財務を圧迫していた。このため、平成17年に「5カ年経営改善計画」を策定、事業再編、財務体質の強化を実施してきたが計画通りの改善を果たせなかった。
こうした中、今年5月1日に(株)サクラダ(東証1部、千葉県市川市、橋梁工事)は同社の子会社化を役員会で決定したと発表。子会社化は実質100%の減資、サクラダの100%子会社が出資する匿名組合で7億円の第三者割当増資を引き受けるというもの。しかし、同社が4月28日に開催した臨時株主総会でサクラダの傘下入りが株主の同意を得られず今後の動向が注目されていた。
なお、関連会社の滋賀釜屋化学(株)(滋賀県蒲生郡竜王町岡屋字三ノ口1535、設立昭和47年5月、資本金1000万円、中野金次郎社長、従業員20名)も同日、東京地裁に民事再生手続開始を申し立てた。負債は約2億7900万円。

(株)コミヤマ工業(甲府市長松寺町6−2、設立昭和23年4月、資本金9600万円、小宮山要社長、従業員253名)は5月18日、甲府地裁に民事再生手続開始を申し立て、25日開始決定を受けた。申立代理人は古井明男弁護士(山梨県甲府市相生1−3−11、電話055−227−9000)ほか。監督委員には田邊護弁護士(甲府市中央1−1−18、電話055−233−7124)が選任されている。負債は債権者約470名に対し約84億100万円(金融債務約53億1600万円、一般債務約30億8500万円)。
同社は昭和21年4月創業、23年4月に法人化した橋梁・建築工事業者。当初は建築工事を中心にしていたが、昭和57年から総合建設に進出、橋梁・一般建築工事に一部住宅建築も手掛け、官公庁からの受注を中心に、ピーク時の平成16年3月期には年商122億8000万円をあげていた。しかし、この間の平成9年に買収した(株)エコテック工業と(株)コミヤマ創建が思惑通りに経営改善を果たせず財務の重荷になっていた。
そうした中、平成17年9月鉄骨橋梁談合事件に関与したとして独占禁止法違反(不当な取引制限)で公正取引委員会から排除勧告を受けた。同社は排除勧告を拒否して審判で争ったが、係争中の平成18年3月期は年商110億400万円にとどまった。
平成18年7月同社は排除勧告に同意、そのため国土交通省関東地方整備局および山梨県から3〜5カ月間の指名停止、22日間の営業停止命令を受けた。さらに、多額の課徴金、罰金の支払いを命じられ完工高、資金繰りは急速に悪化、現状での自力再建が困難な状況から民事再生法による再建を図ることになった。
記事の引用・リンクについて
記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。
(記載例) 東京商工リサーチ TSR速報 ※当社名の短縮表記はできません。
詳しくはサイトポリシーをご確認ください。
関連サービス
人気記事ランキング


【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学
全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。
2

2025年「介護事業者」の休廃業・解散653件 苦境の「訪問介護」が押し上げ、過去最多を更新
2025年の「介護事業者」は、倒産以外で事業を停止した「休廃業・解散」が653件(前年比6.6%増)に達し、 4年連続で最多を更新した。
3

融資慣行に変化、「事業性融資推進法」が施行目前~ 金融庁・大城健司参事官 単独インタビュー ~
2026年5月「事業性融資の推進等に関する法律(事業性融資推進法)」がスタートする。「企業価値担保権」の導入により、企業の実力や将来性、無形資産を含む事業全体を担保にした融資が可能になる。 事業性融資を推進する背景や想定される課題を金融庁総合政策局の大城健司参事官に聞いた。
4

ジュピターコーヒーに民事再生開始決定、承継店舗が判明
1月5日に東京地裁に民事再生法の適用を申請したジュピターコーヒー(株)(TSRコード:292914610、文京区)は1月13日、同地裁から民事再生開始決定を受けた。また、スポンサーが承継予定の47店舗がわかった。
5

「不動産業」 上位4%の大手がシェア約8割 地価上昇と活発な実需・投資が追い風に
売買を主力とする主な不動産業6,090社の最新期決算(2024年7月期-2025年6月期)は、売上高が17兆3,430億円(前期比7.9%増)と好調だったことがわかった。純利益も1兆3,063億円(同6.8%増)で、純利益率7.5%と高収益を持続。7年間では売上高、利益とも最高を記録した。