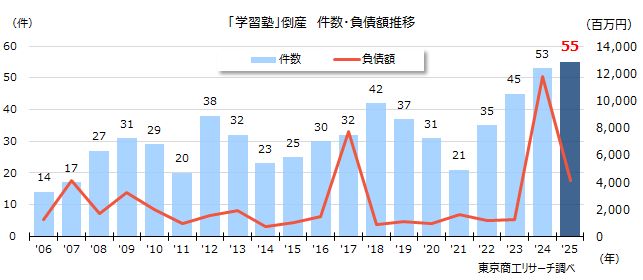DXへの取り組み、中小企業は4割にとどまる 予定なしも約2割 「生産性向上」目的が7割、中小企業は「金融機関」活用が最多
~「DXに関するアンケート」調査~
アフターコロナに向け、新規事業の開拓や人手不足への対応でDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進の重要性が増している。だが、DXに取り組んでいる中小企業は40.6%で、大企業の66.0%を25.4ポイント下回ることがわかった。また、DXへの取り組みに支援機関を活用する意向の中小企業は約5割(48.0%)で、半数近くがDX推進に外部支援を求めている。東京商工リサーチ(TSR)が8月にアンケート調査を実施した。
DXに取り組む中小企業の42.6%が支援機関として「金融機関」をあげた。伴走支援で、DX支援に取り組む地域金融機関が増えているが、企業側も金融機関のDX支援の必要性に言及している。
中小企業の約4割(41.2%)は、DX投資への予算が「500万円未満」だった。会計や労務などのバックオフィスDXはパッケージソフトの利用が容易で、低予算での対応も可能なケースが多い。
だが、売上や利益の拡大、新規顧客の開拓などを目的にするフロントオフィスDXは、開発費用が嵩むだけに、中小企業には負担が大きくなっている。
中小企業のDX推進を後押しする経済産業省は2023年4月、「中堅・中小企業等向け『デジタルガバナンス・コード』実践の手引き2.0」を公表した。「IT導入補助金」や「DX投資促進税制」など、各種支援施策の周知も含め、事業者がDXに取り組みやすい環境整備に取り組んでいる。
だが、中小企業がDXを導入しやすくするための支援策と並行して、DX導入後の具体的な効果について、おざなりでない身近な業務に落とし込んだ細やかな情報提供も必要だろう。
※本調査は、2023年8月1日~9日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答5,030社を集計・分析した。
※資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。
Q1. 貴社ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいますか?(択一回答)
DXへの取り組み、規模による差が顕著
DXに「取り組んでいる」が43.6%(5,030社中、2,196社)、「取り組んでいないが、必要性を感じている」が39.2%(1,975社)、「取り組む予定はない」は17.0%(859社)だった。
規模別では、「取り組んでいる」は大企業が66.0%(595社中、393社)なのに対し、中小企業は40.6%(4,435社中、1,803社)で、25.4ポイントの大幅な差がついた。「必要性を感じている」を合わせると、大企業は95.1%(566社)がDXに前向きな姿勢を示したが、中小企業は81.2%(3,605社)にとどまった。
業種別では、「取り組んでいる」の割合が最も高いのは受託開発ソフトウェア業などの「情報サービス業」の65.9%(285社中、188社)だった。

Q2. Q1で「取り組んでいる」「取り組んでいないが、必要性を感じている」と回答した方に伺います。貴社の業務において、DXに期待する効果は何ですか?(複数回答)
「業務効率化による生産性の向上」が7割超
4,029社から回答を得た。
最多は、「業務効率化による生産性の向上」の74.7%(3,013社)。以下、「業務時間削減」が65.3%(2,633社)、「人的ミスの低減」が55.0%(2,218社)の順。効率化やインシデント防止、従業員の労働負荷の低減を目的にDXに取り組む企業が多い。
経済産業省はDXの定義を「データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと」としている。だが、「売上・利益の拡大」は27.2%(1,096社)、「新規顧客の開拓」は12.5%(506社)にとどまった。
規模別では、「業務時間削減」が大企業で75.8%(551社中、418社)なのに対し、中小企業は63.6%(3,478社中、2,215社)で12.2ポイント下回り、規模による差が最大だった。
コロナ禍以前から時間外労働の上限規制の適用を受けていた大企業は、業務時間の削減におけるDXニーズが強いとみられる。

Q3. Q1で「取り組んでいる」「取り組んでいないが、必要性を感じている」と回答した方に伺います。DXに取り組むにあたり、支援機関を活用しましたか?(択一回答)
約5割が支援機関の活用に言及
DXへ取り組む際の支援機関の活用状況について、3,942社から回答を得た。
「支援機関を活用した(活用している)」が14.8%(585社)、「現在は活用していないが、活用を検討している」が32.6%(1,288社)で、47.5%(1,873社)が支援機関の活用に言及した。
規模別では、大企業の「活用した」「活用を検討」の合計が44.2%(228社)に対し、中小企業は48.0%(1,645社)で3.8ポイント上回った。
大企業と比べ人的リソースが乏しい中小企業では、社内でのDX対応が難しく、外部の支援を必要としているとみられる。

Q4. Q1「取り組んでいる」「取り組んでいないが、必要性を感じている」と回答した方に伺います。今年度のDX投資の予算はいくらですか?(択一回答)
最多レンジは「100万以上500万円未満」
今年度のDX投資の予算について聞いた。3,659社から回答を得た。
予算の最多レンジは「100万以上500万円未満」の21.9%(804社)だった。以下、「100万円未満」の17.4%(640社)、「500万円以上1,000万円未満」の8.1%(299社)、「1,000万円以上5,000万円未満」の5.6%(206社)と続く。
「現時点で予算は決めていない」は45.2%(1,657社)だった。
規模別では、「100万円未満」の大企業が9.8%(428社中、42社)に対し、中小企業は18.5%(3,231社中、598社)、「100万円以上500万円未満」の大企業が15.8%(68社)に対し、中小企業は22.7%(736社)で、それぞれ中小企業の構成比が上回った。一方で、それ以上のレンジはすべて大企業の割合が上回り、企業規模による資金力の差がDX投資の予算にも影響していることが見て取れる。

Q5. Q3で「支援機関を活用した(活用している)」「現在は活用していないが、活用を検討している」と回答した方に伺います。どのような支援機関を活用、または活用を検討していますか(複数回答)
4割が「金融機関」を活用
支援機関の活用に言及した1,692社から回答を得た。
最多は「ITベンダー」の42.0%(711社)だった。次いで、「金融機関」の40.7%(689社)、「コンサルタント」の28.4%(481社)の順。その他では、「東京都DX人材リスキリング支援事業」(建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、資本金1億円未満)など、自治体主導による支援を挙げる企業が多かった。
規模別では、大企業の最多は「ITベンダー」の66.8%(199社中、133社)だった。次いで、「コンサルタント」の41.2%(82社)で、それぞれ中小企業の38.7%(1,493社中、578社)、26.7%(399社)を28.1ポイント、14.5ポイント上回った。
一方、中小企業の最多は「金融機関」の42.6%(637社)で、大企業の26.1%(52社)を16.5ポイント上回った。
地域金融機関による伴走支援の一環として、中小企業向けDX支援の取り組みも進められている。大企業に比べてDX投資の予算が少ない中小企業は、金融機関や商工会等の支援を利用する割合も高くなっている。